2365 【吉村外喜雄のなんだかんだ】
心と体の健康
「スマホ、長時間使用による弊害(2)」 スマホの使い過ぎは、短期的な脳障害だけで
なく、長期的にも深刻な影響を及ぼします。
習慣化すると、情報のインプットが多すぎて
「脳疲労」の状態に陥る弊害が問題になって
いる。
情報は、脳の「前頭前野」で処理している。
① 浅く考える機能
② 深く考える機能
③ ぼんやりと考える機能 絶えずスマホを見て情報をインプットしてい
ると①の機能ばかり使うことになり、脳は
へとへとに・・②③の機能は使われなくなる。 最近の研究で、③の時に働く機能が、脳に
大変重要な働きをすることが分かってきた。
ぼんやりしている時に、情報の整理や分析を
行い、人間の本質に関わる思考を培ったりす
る。
この機能が低下すると自分を客観視でき
なくなり、手短な快楽に流されるようになる。 スマホの使い過ぎは、眼底疲労、視力の低下
ドライアイなどの目の病、睡眠時間の不足に
よる睡眠障害など、長期間に及ぶと慢性化し
、日常生活に大きな不具合をもたらします。 精神面でも、依存症やうつ病、精神的不安症
に悩まされるようになる。
心と体の健康
「スマホ、長時間使用による弊害(2)」 スマホの使い過ぎは、短期的な脳障害だけで
なく、長期的にも深刻な影響を及ぼします。
習慣化すると、情報のインプットが多すぎて
「脳疲労」の状態に陥る弊害が問題になって
いる。
情報は、脳の「前頭前野」で処理している。
① 浅く考える機能
② 深く考える機能
③ ぼんやりと考える機能 絶えずスマホを見て情報をインプットしてい
ると①の機能ばかり使うことになり、脳は
へとへとに・・②③の機能は使われなくなる。 最近の研究で、③の時に働く機能が、脳に
大変重要な働きをすることが分かってきた。
ぼんやりしている時に、情報の整理や分析を
行い、人間の本質に関わる思考を培ったりす
る。
この機能が低下すると自分を客観視でき
なくなり、手短な快楽に流されるようになる。 スマホの使い過ぎは、眼底疲労、視力の低下
ドライアイなどの目の病、睡眠時間の不足に
よる睡眠障害など、長期間に及ぶと慢性化し
、日常生活に大きな不具合をもたらします。 精神面でも、依存症やうつ病、精神的不安症
に悩まされるようになる。
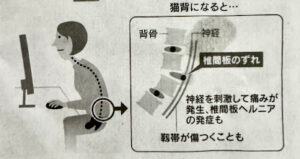
特に、下向き姿勢や顔面凝視などによる姿勢
の悪化が原因でストレートネック「スマホ首」
になり、頭痛肩こり、集中力の低下、物忘れ、
などの症状が表れ、自律神経の乱れや認知
機能への影響が指摘されます。
これらは「スマホ症候群」と呼ばれ、現代病
の一つになっている。
